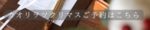- ホーム
- 台所薬局/レシピ・コラム
台所薬局/レシピ・コラム

Lemon
2012/07/07
英名: Lemon
学名: Citrus limon
科名: ミカン科
主産地: イタリア
抽出部位: 果皮
抽出方法: 圧搾法
ノート: トップノート
What's 食べるアロマレモン?
健康を気にして食生活を見直す人が増えてきてます。
オーガニックやローフード(RawFood=すべての食べ物のイノチを活かすために、加熱調理をしない、生の食品を摂取すること)を取り入れたり、
サプリメントを摂取したりする人も多いはず。
中にはサプリメントが食事代わりという方もいるかもしれませんね。
米国の研究では、
現代人はサプリメントの栄養素の半分も体内に取り入れられてないという報告があります。
それは、ストレスやタバコ、アルコール、酸性食品過多による酸性体質のため、細胞膜が厚くなり、
せっかく運ばれた栄養素を細胞内に取り込むことが出来なくなってきているというのです。
サプリメントを摂取して安心と思っていたら、半分も吸収されず排泄していたなんてびっくりですね!
1滴のレモン精油。
食事の前にコップの水に1滴たらして飲むことで、
この精油が栄養運搬系を引き受けてくれます!
精油の分子はとても小さいので、
厚くなった細胞膜を通過し細胞の中の中まで酸素とともに栄養を送り届けてくれるのです。
「精油って飲んでいいの?」と驚く人もいるかと思います。
確かに日本では外用のみで服用は認められていません。
でも海外ではミルクや蜂蜜に混ぜて内服するのはポピュラーな自然療法。
アロマテラピーの翻訳本等で紹介されているので知ってる方もいらっしゃるでしょう。
自然の恵みのエネルギー溢れる1滴を取り入れてみませんか?
体、いっぱいに自然の力がみなぎる感覚が味わえるはずです。
【注意】コップ1杯の水に精油(エッセンシャルオイル)1滴を目安に薄める事を忘れないようにしましょう。 また、飲用に際してはお客様の御判断でお願いします。
〈レモンエッセンシャルの特徴〉
レモンはビタミンCが多く含まれており、お菓子や料理などに利用される、
酸っぱくさわやかな香りの果実。
レモンの精油(エッセンシャルオイル)は、果実の圧搾法から作られます。
気分をリフレッシュしたいときは、ルームフレグランスとして
利用するのも良いでしょう。抗ウイルス作用があるので、感染症や
風邪の予防にも最適です。ニキビや脂性肌の皮脂バランスをととのえ、
肌を引きしめる効果もあります。
〈レモンエッセンシャルの香りの特徴〉
レモンを切った瞬間のような、フレッシュでさわやかな香り
〈ノート〉トップノート
〈心への作用〉
気分をリフレッシュさせます。集中力をアップさせます。
〈体への作用〉
風邪からくる発熱や、のどの痛みにききます。
感染症を予防し、頭痛などの痛みをやわらげます。
血のめぐりを良くするので、貧血やむくみに効果があります。
〈肌への作用〉
ニキビやシワ、脂性肌に効果あり。つめや髪の毛を強くします。
その他の効能キーワード
冷え性、便秘、殺菌、腐食、止血、収れん、利尿
〈相性の良い精油〉
イランイラン、カルダモン、ジュニパー、ネロリ、フランキンセンス、
リンデン、ラベンダー、ローズ、カモミール、ベンゾイン
〈使用上の注意点〉
敏感肌の方は使用量には注意してください。
光毒性がありますので、利用した後は数時間日光に当たらないでください。
アロマテラピーは医学ではありません。精油をご利用の際は、製品についている注意事項を
よく読んでお使いになってください。妊娠中の方や、重い病気・慢性的な病気がある方など、
心身の健康状態が気になる方は必ず医師に相談して精油をご利用ください。
アロマテラピー芳香浴法
2012/07/07芳香浴とは
芳香浴はアロマテラピーを気軽に楽しむ最もポピュラーな方法です。
天然のアロマエッセンシャルオイルを使って、お部屋にやさしい香りを充満させることで、
日常のストレスから解放され、ゆったりとした気分を味わうことが出来ます。
毎日の生活に香りをプラスして、いつもと少しだけ違った時間を過ごしてみませんか?
アロマポット (オイルウォーマー)
▼使い方と特徴▼アロマテラピー芳香浴法
アロマポット(オイルウォーマー)は、キャンドル式のアロマ芳香器です。
上部の受け皿にお湯や水を入れた後、アロマエッセンシャルオイルを3~10滴たらして使います。
器の下にキャンドルをセットし、火をつけると、オイルが揮発し、香りがお部屋に広がります。
香りが立ちやすく、比較的安価で手に入るのが特徴です。
キャンドルを使用するため、火の取扱いには十分注意する必要があります。
就寝時には、必ず火を消しましょう。
アロマランプ (アロマライト)
▼使い方と特徴▼
アロマランプ(アロマライト)は、電球の熱を使ったアロマ芳香器です。
アロマポットと同様に、アロマオイルを温めて香りを広げます。
上部の受け皿にお湯や水を入れた後、アロマオイルを3〜10滴たらして使います。
スイッチを入れると電球が灯り、やさしい光と香りがお部屋に広がります。
火を使わないため安全で、就寝時でも安心して使用することが出来ます。
アロマポットに比べ価格は高めですが、デザインも豊富で、お部屋のインテリアとしても楽しめます。
アロマディフューザー (超音波式/スチーム式)
▼使い方と特徴▼
ミスト(霧)が出るタイプのアロマ芳香器です。アロマミスト、アロマ加湿器とも呼ばれます。
超音波振動板で水を振動させ、冷たいミストを発生させる「超音波式」のものと、タンクの水を加熱し、熱い蒸気を発生させる「スチーム式」のものがあります。
超音波式のものが一般的で、種類も豊富です。加湿量はそれほど多くありません。
スチーム式のものは加湿量は多めですが、熱い蒸気が出るためやけどなどに注意が必要です。
目に見えるミストが発生するため、視覚的にも楽しめます。イルミネーション機能を備えたものもあります
芳香浴の手軽な楽しみ方
アロマポットやアロマランプ、ディフューザーといった器具を使わなくても、手軽に芳香浴を楽しむことが出来ます。
マグカップ
マグカップにお湯を注ぎ、アロマエッセンシャルオイルを1〜2滴たらして、立ち上る蒸気を吸い込みます。
蒸気がせきを誘発する場合もありますので、喘息の方は控えたほうが良いでしょう。
ハンカチ、ティッシュ、コットン
ハンカチやティッシュにアロマエッセンシャルオイルを1〜2滴たらして、香りを楽しみます。
枕元やデスクに置けば手軽に香りが楽しめますし、外出先でも香りを楽しむことができます。
ハンカチを使う場合は、オイルの種類によってはシミになることもありますので注意が必要です。
また、応用として、マスクにオイルをたらす方法もあります。花粉のシーズンなどにおすすめです。
(皮膚や唇に直接オイルが触れないようにしてください。)
アロマバス法
2012/07/07アロマバスとは
アロマバスは、温かいお湯をはったバスタブにアロマエッセンシャルオイルを数滴たらして、ゆっくり肩までつかったり、半身浴を楽しんだりする方法です。バスタイムは、筋肉の緊張をときほぐしてくれる貴重な時間です。そんな大切な時間をもっと充実させるために、アロマバスはピッタリの存在なのです。
心と体をリラックスさせてくれる入浴に、アロマエッセンシャルオイルの持つ香りの効果がプラスされることで、さらなるリラックス効果が期待できます。体の疲れている部分をもんだりさすったりしながら、ゆったりとした時間を過ごして下さい。
全身浴
バスタブにぬるめのお湯をはり、5滴ほどのアロマエッセンシャルオイルをたらし、よくかきまぜてからゆったりとつかります。心地よい香りが、浴室いっぱいに広がります。
アロマエッセンシャルオイルは水に溶けにくいため、オイルの原液が直接お肌についてしまうことがあります。お肌の弱い方は、アロマエッセンシャルオイルを5ml程度の少量のキャリアオイルで薄めてから使用すると良いでしょう。
また、柑橘系のアロマエッセンシャルオイルを使用する場合、お肌の敏感な方はピリピリとした刺激を感じることがあります。そのような場合は、オイルの量を減らしたり、使用を中止して下さい。
半身浴
肩までたっぷりとつかる全身浴に対して、心臓の下くらいまで長時間つかるのが半身浴です。 5滴ほどのアロマエッセンシャルオイルをたらし、よくかきまぜてからゆったりとつかります。 心臓に負担を掛けにくく、また下半身を温めることによって芯から体を温めることができます。 ぬるめのお湯に30〜40分程度入りましょう。
汗が出るため、入浴前には十分な水分を補給します。 上半身が冷える場合は、バスタオルなどを肩にかけるとよいでしょう。
手浴(ハンドバス)
洗面台のシンクや洗面器にお湯をはり、アロマエッセンシャルオイルを2〜3滴たらして両手を浸します。同時に蒸気を吸い込むようにすれば、芳香浴を楽しむことも可能です。指先だけでなく上半身を温めることができますので、肩や首の健康にもおすすめです。ひじをお湯につける「ひじ浴」という方法もあります。
足浴 (フットバス)
簡単に足元から体を温める方法です。大きめの洗面器やバケツに熱めのお湯をはり、アロマエッセンシャルオイルを3滴ほどたらします。両足首を入れ、10分ほどつかります。足首や指先のストレッチを行なうとより効果的です。
座浴
大きめの洗面器を利用して、お尻までつかるアロマバスを座浴といいます。
お湯にアロマエッセンシャルオイルを1滴たらし、お尻を洗うようなイメージで2〜3分間つかりましょう。
バスソルトの作り方
バスソルトとは
バスソルトとは、ミネラルを沢山含んだ天然塩にアロマエッセンシャルオイルを混ぜたものです。 塩を使った入浴法はよく知られていますが、そこにアロマエッセンシャルオイルを加えることでアロマテラピー効果も期待できます。
1回の入浴に使う天然塩の量は30〜50gです。お肌の敏感な方は、塩による刺激を感じる場合がありますので、量を少なめにして下さい。
作りおきできるのも便利です。余ったバスソルトは密閉容器で保存して下さい。
バスソルトの作り方
天然の塩(30〜50g)をボウルに入れて、5滴ほどのアロマエッセンシャルオイルを加えます。
塩とオイルが均一になるようにかき混ぜます。
出来上がったバスソルトをバスタブに入れ、よくかき混ぜてから入浴します。
アロマトリートメント法
2012/07/07アロママッサージ
アロマオイルの香りと成分を利用したアロママッサージは、アロマテラピーの1つの醍醐味ともいえます。 心地よい香りと、マッサージのソフトな感触は、1日の疲れを忘れさせてくれます。 高いサロンに行かなくても、アロママッサージは自宅で簡単に行なうことが出来ます。 はじめるとクセになるアロママッサージで、夜のひとときを楽しくしてみませんか?
アロママッサージをはじめる前に
アロマオイル(精油)は原液のまま使用しない
アロマオイル(精油)の原液を直接お肌につけることは出来ません。 ホホバオイルなどのキャリアオイル(植物油)で、必ず1%以下に希釈します。
敏感肌の人はパッチテストを
お肌の敏感な方は、事前にパッチテストを行なうことをおすすめします。 二の腕の内側など敏感な部分に希釈したアロマオイルを少し塗って、数時間から1日様子を見ます。 赤みや腫れが出なければ大丈夫です。
妊娠期の方や乳幼児は控える
アロママッサージでは、アロマオイル(精油)の有効成分が直接かつ広範囲から体内に取り込まれます。
アロマオイル(精油)の種類によっては健康に影響を与える場合もありますので、妊婦の方や3歳未満の乳幼児には、アロマオイル(精油)を使ったマッサージは行なわないようにして下さい。
(医師の指導のもとで適切に行なわれる場合は問題ありません)
アロママッサージの効果を高めるために
アロママッサージは、お風呂上りがもっとも効果的です。 体が清潔で、血行も良く、気分的にもリラックスしているからです。 部屋は暑すぎず、寒すぎずの状態にしておきましょう。 リラックスできる音楽を流したりすると、さらに効果的です。 マッサージの後は洗い流さず、一晩じっくり浸透させます。 ベタつきが気になるときは、タオルで軽くふき取って下さい。
マッサージオイルの作り方
マッサージオイルは、アロマオイル(精油)をキャリアオイル(植物油)で希釈して作ります。 アロマオイルの濃度は1%以下を目安にします。 使用するアロマオイルとキャリアオイルの量は以下の通りです。 (数種類のアロマオイルをブレンドする場合は、合計で以下の量になるようにします)
キャリアオイルとは
キャリアオイルとは、マッサージオイルをつくるときにベース(基材)となる植物油のことです。 アロマオイルが肌の奥深くに浸透するのを助けることから、キャリアオイル(carrier=運ぶもの、媒介)と呼ばれます。
たくさんの種類がありますが、好みや使用感、目的などに応じて選びます。
アロマオイルを使わず、このキャリアオイルだけでマッサージをすることも出来ます。
食用の植物油とは異なり、マッサージ用の植物油は主に低温圧搾法という方法で搾油されています。
植物油本来のナチュラルな成分をお肌に使用するため、キャリアオイルはアロマテラピーショップ等で販売されているマッサージ用のものをご利用下さい。
アロマハウスキーピング
2012/07/07アロマオイルでハウスキーピング
アロマエッセンシャルオイルを使って、家の中を清潔に保つことができます。 殺菌、抗菌、消臭効果のあるアロマオイルを使い、ハウスケアができます。 爽やかな香りで、毎日のお掃除も楽しくなってきます。
アロマオイルを使った方法
アロマエッセンシャルオイルの原液を、そのまま使う方法です。
ユーカリやティートリーなどのオイルを床を磨く雑巾やシートにたらしたり、掃除機のごみパック部分にたらして使います。嫌な匂いが消え、心地よい香りが広がります。
また、洗濯のすすぎのときにオイルを1〜2滴入れると、生乾きの嫌な匂いをおさえたり、洗濯物をほのかに香らせたりすることが出来ます。
消臭スプレー(ルームフレッシュナー)を使った方法
アロマオイルを使って消臭スプレーを作ります。 お部屋の気になる部分にシュッとスプレーするだけで、さわやかな香りが広がります。
消臭スプレー(ルームフレッシュナー)の作り方
無水エタノール 5ml
アロマオイル(精油) 15滴
精製水 25ml
ビーカー
ガラス棒
保存容器 (スプレー式の遮光ビン)
ビーカーに無水エタノールをいれ、アロマエッセンシャルオイルを加えます。
ガラス棒でよくかき混ぜた後、スプレー容器に移します。
ビーカーで精製水を計り、さきほどのスプレー容器に移します。
よく振って出来上がりです。 スプレーを使用するときには、よく振るようにします。
消臭パウダーを使った方法
ごみ容器の匂いを消すため、底の部分に消臭パウダーを敷いておくと効果的です。 匂いを吸収する重曹に、ユーカリやティートリーなどのアロマオイルを加えます。
消臭パウダーの作り方
重曹 100g
アロマエッセンシャルオイル 適量
小鉢などに重曹を入れ、アロマオイルを加えます。 はしや竹串でよくかき混ぜて出来上がりです。
精油選びのポイント
2012/07/07
ホーム 選ぶ時のポイント
アロマオイルは、世界中のさまざまなメーカーが、さまざまなブランド名で販売しています。 「一体どれを選んだらいいの?」という声が聞こえてきそうですが、まずは以下の点に気をつけると良いでしょう。
100%天然(ピュア&ナチュラル)か
学名、原産国、抽出部位、抽出方法が記載されているか
容器に遮光ビンが使われているか
適正な価格か
ピュア&ナチュラルなアロマオイル(精油)
ピュア&ナチュラルというのは、アロマオイル選びの絶対条件です。
アロマオイルは、自然の原料から作られたもの(ナチュラル)で、なおかつ、他のオイルなどと混ぜたりしていないもの(ピュア)を使用します。 100% Pure & Natural、Pure Essential Oil、などの表記があれば、ほぼ問題ないでしょう。
一方、石油原料などから化学的に合成したもの(合成)や、メリッサ、レモングラスのような似た香りの精油を混ぜたもの(偽和)、精油成分の調整を行なったもの(混和)、あるいは、高額な精油の組成データに似せて人工的に成分をつぎはぎしたもの(ネイチャーアイデンティカル)などは、アロマテラピーで用いるべきではありません。
ラベルの記載事項
植物は学問上の名称としての「学名」を持っています。
例えば、「グレープフルーツ」は一般的な名称ですが、学名は「Citrus paradisi」と言います。
アロマオイルのラベルに原料となった植物の学名や原産国を表示する義務はありませんが、このような表示のあるものは、メーカーの姿勢が表れており、安心して使えます。
なるべく、「学名」、「原産国」、「抽出部位」、「抽出方法」、「発売元(輸入元)」、「注意事項」などが明記されているアロマオイルを選びましょう。社団法人日本アロマ環境協会では、健全なアロマテラピーの普及のため、精油の表示認定制度を行なっていますが、この認定を得るためには上記事項を明記する必要があります。
アロマオイル(精油)の容器
アロマオイル(精油)はポリ容器を劣化させるため、必ずガラス容器に入れておく必要があります。 日光の影響を受けやすいため、青色や茶色などの遮光ビンに入っているものを選びましょう。
アロマオイル(精油)の価格
最近はさまざまな場所でアロマオイルを販売しているのを見かけるようになりましたが、極端に金額が安いもの(100円ショップなどで購入できるもの)は、ピュアなエッセンシャルオイルではありませんので、避けたほうが良いでしょう。
日本国内の場合、例えばラベンダーの10mlサイズで2500円〜3000円程度、5mlサイズで800円〜1000円程度のものが多いようです。 最近は成分分析表を添付しているアロマオイルも増えてきました。
成分を分析しているからといって必ずしも成分がすぐれているとは限らないのですが、こういったメーカーのアロマオイルは安心感があります。ただし、価格はその分高めです。
自分に合ったアロマオイル(精油)を
アロマテラピーの知識がついてくると、「○○の成分は何%ですか?」といった、細かな精油の成分にとらわれる人が増えてきます。そうして選んだ精油が自分に合っていれば問題はないのですが、もし好きでもない香りを、「これは成分的に優れているから」といった理由で使い続けているとしたら、それは大変残念なことです。
精油がクスリと大きく異なるのは、精油が数十から数百の芳香成分からなる有機化合物である点です。これらが調和して一つの香りを作りあげているところに、アロマテラピーの面白さがあります。
このトータルとしての香りを心地よく感じるかどうかというのは、アロマテラピーを行なう上で非常に大切です。人は心地よいと感じたときに、はじめて安らぎを実感することができるのです。
アロマオイルは、同じ種類のものでもメーカーにより微妙に香りが異なります。
同じ品種のぶどうを使ったワインでも、産地によって味や香りが異なるように、同じラベンダーオイルでも、産地が異なれば香りも異なってきます。
まずは自分の好みに合ったアロマオイルを選ぶことからはじめましょう。